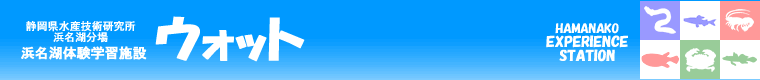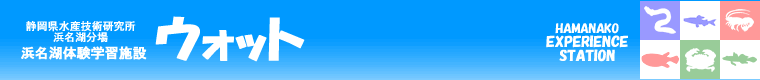|
ホーム > ウォット広場 > 学習ページ > 海も必要な淡水魚
 海も必要な淡水魚 海も必要な淡水魚 
|
河川や湖沼に生息する魚類は淡水魚と呼ばれ日本には約180種が生息していますが、このうちの100種以上は生涯のうちのある時期に海が必要な淡水魚です。そのため淡水魚は海との関わり方によって、純淡水魚、通し回遊魚、周縁性淡水魚に区分されています(第1表)。
純淡水魚はコイやメダカなどの淡水域で一生を生活するものを、周縁性淡水魚はマハゼやボラなどの本来は海水魚でありながら汽水域(淡水と海水が混じる水域)で生活したり、一次的に淡水域に進入する魚を指します。
第1表 淡水魚の区分
水野信彦・後藤晃 編 「日本の淡水魚類 その分布、変異、種分化をめぐって」を一部改変)
| 区分 |
種名 |
| 純淡水魚 |
コイ、ナマズ、メダカ、カワヨシノボリなど |
| 通し回遊魚 |
降河回遊魚 |
ウナギ、アユカケなど |
| 遡河回遊魚 |
シシャモ、サケ、サツキマスなど |
| 両側回遊魚 |
アユ、ウツセミカジカ、多くのハゼ科魚類など |
| 周縁性淡水魚 |
マハゼ、スズキ、ボラ、クロダイなど |

コイ |

メダカ |

マハゼ |

ボラ |
|
|
★通し回遊魚★
通し回遊魚とは海と淡水域との間を定期的に回遊しているもので、ウナギ、シシャモ、サケ、アユ、ハゼ類など産業的に重要な魚種が多く含まれます。
ウナギは産卵のために川を下り遠く西マリアナ海域で産卵します。また、アユカケという魚も普段は河川中流域に生息していますが、晩秋から初冬になると産卵のために降河し河口や沿岸の転石の下で産卵します。
浜名湖では11月下旬頃から降河個体が確認され、12〜2月頃まで産卵が行われているようです。このように普段は河川に生息し産卵のために川を下るものを降河回遊魚と呼びます。

ウナギ |

アユカケ |
反対に、普段は海に生息し産卵のために河川を遡上するものを遡河回遊魚と呼び、シシャモやサケなどが知られています。
一方、アユは生まれて直ぐに海へ下り海域や河口域で冬を過ごした後に、春になると河川を遡上して河川内で成長するようになります。このように産卵のためではなく幼魚期に海と川とを往来するものを両側回遊魚と呼び、アユ以外にはハゼ類などが知られています。

アユ |
|
★都田川の淡水魚★
ところで、浜名湖奥部に注ぐ都田川で水産試験場が確認した46種の淡水魚のうち、14種が通し回遊魚、7種が周縁性淡水魚でした。また、都田川下流域で平成12年10月から平成13年9月まで毎月実施した仔魚調査では、海に向けて降下している仔魚が毎月採集されました。
このように川と海との繋がりは日本産淡水魚にとっては無くてはならないもののようです。しかし近年、ダムや堰堤などの河川構造物の存在や河口域の汚濁などにより降河・遡上行動が制限されてしまう例が多数報告されています(第1図、第2図)。淡水魚が安心して生息できるような河川環境の保全・復元が急務と思われます。
第1図 河川工作物
(農業取水のための堰堤)

|
第2図
遡上を妨げられるウキゴリ類の稚魚(手前)
奥に見えるのはボウズハゼ稚魚

|
ボウズハゼ稚魚は口と吸盤を使って堰を越えていくが、遡上力が劣るウキゴリ類の稚魚は堰堤下に群で滞留してしまう。 |
|
(解説:旧水産試験場浜名湖分場 鈴木邦弘) |
|
Copyright © 2001-2016 ウォット All rights reserved.
|
|